| 仙台の厚い夏 1987年のことです。 法則化仙台合宿がおこなわれました。 私は、この合宿に論文を100本持っていきました。 4月から書き始めて3か月。100本を書き上げたのです。 この間、学級通信も350号書きました。 もちろん、授業をちゃんとやり、校務もちゃんとやった上での話です。 今考えても、すさまじいことをやったと思います。 この修行につきあってくれたのが、平和氏、阿部氏です。 3人で300本持っていきました。 山のように積まれた論文は、参加者を圧倒しました。 時間活用術をはじめ、知的生産に関する本を100冊以上読みました。 いいと思ったことを実行しました。 大量の論文を書く取り組みで、たくさんのことを学びました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
序章 前人未踏の偉業 「仙台の厚い夏」は、歴史に残る偉業を成し遂げた。それは、
前人未到の偉業といっていい。 これまでに、100本論文を書いた人はいる。 しかし、1つの合宿に100本論文を持っていった人はいない。 普通の人に「1合宿100本論文」の発想はない。 大変だからである。 バカらしいからである。 執筆するためには、書くべき内容がなくてはならない。 100本分の実践があることが前提になる。 我々は作家ではない。 1日中論文を書いているわけにはいかない。 やるべきことがたくさんあるからである。 4月~7月末の4か月間で100本書く… 非常に厳しい。 製本も大変である。 以上のことから。「1合宿100本」という発想は生まれない。 「仙台の厚い夏」のすごさは、その発想と行動力にある。 不可能といえることを発想し、実際にやり遂げる。 すさまじい情熱とパワーである。 我々は、前人未到の未到の偉業に挑戦した。 本当に目標を達成できるかどうかわからなかった。 3人とも、何度も何度も挫折しそうになりながら命がけでやったのである。 合宿以後、3人は大きく成長した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1章 論文100本への道 仙台合宿に向けて、サークルを創った。 その名も「仙台の厚い夏」 東京連合結成される! 4月2日 執筆者 杉渕 その名も「仙台のあつい夏」 3月29日(京都合宿帰り、新幹線の中で)法則化東京連合が結成された。 その名も「仙台のあつい夏」。 なお、「仙台のあつい夏」は、8月4日で解散する予定。 仙台合宿で「東京のパワーをみせてやろう」というのが、連合発足の理由である。 ★メンバー 代表 阿部(美園座ぶどう塾代表) 阿部夫人(美園座ぶどう塾事務局長) 平和(武蔵野サークル代表) 中島(多摩なでしこ会) 杉渕(ほっぷ代表) 連合結成までのいきさつ ことの発端は、京都合宿、夕食のときの杉渕発言である。 「仙台合宿には、論文を50本持っていきます」 大きな反響を呼んだこの発言。 「できっこないじゃないか」 「いや、杉渕ならやるかも…?」 私は半ば冗談、半ば真剣に考えていた。 合宿終了後、法則化相生代表の松本氏がやってきた。 「杉渕先生、ぼくも仙台合宿には50本持っていきます」 「えーっ、松本さんも宣言するの?」 「はい、今、舘野先生(仙台合宿の事務局長)に頼んできたんですよ。席は杉渕先生のとなりにしてくださいって。こんなに高く積み上げられた論文が続くなんて、考えるだけで楽しくなってしまいますね」 富士山の、いや、チョモランマのごとく高く積み上げられた論文の山を想像してしまった。 「雲がかかる論文」 これはおもしろい。 仙台合宿がおもしろくなってきた。 私は、明治図書の樋口編集長に、原稿用紙を送ってくださいと頼んだ。 合宿終了後、阿部夫妻、平和氏、杉渕の4人は、大原の三千院にいった。 三千院を見てから、にしんそばを食べた。 食べながら、美園座ぶどう塾 今年度(1987)の企画を練った。 阿部夫人、平和氏、中島氏が、今年度は5年生担任。 年間共通教材を選び、教材研究をしようという話になった。 「それはいいね。それを論文にして、仙台へ持っていけば?」 「そうだ、それを論文にすればいいんだ」 「ひとり20本書いて持っていったらどう?」 「平和さん、横着しちゃダメよ」 「そ、それをいわれると、つらいなあ、ははははは…」 外を見ると、もう、真っ暗。 時計を見ると、6時半近い。 私たちは、急いで店を出た。 「仙台のあつい夏」結成される 帰りの新幹線の中、阿部氏は、美園座ぶどう塾の年間計画を立てていた。 私は、学級通信の構想を練っていた。 この2人は、たがいに口をはさみながらあーだこーだとやっていたのだが、そのうち、例の杉渕発言が話題になった。 「本当に、50本持っていくと思う?」 「いったことは、必ずやるからな、杉渕は」 「えっ、じゃあ、今年中に結婚するぞ」(笑) 「それは、すごい反例だ」(笑) 何がすごいのかよくわからない。 ちなみに、私は結婚できないのではなく、まだ結婚しないのである。 ※結婚したのは、この4年後 話を元に戻す。 「阿部は、どうするんだよ」 「うーん」 阿部氏の口が重くなっているときは、何か秘密があるときである。 長年のつき合いから、「こいつ、50本ねらっているな」と直感した。 「阿部、おまえ、50本ねらっているんじゃない」 私は確信したようにいった。 「実は、おれも50本書こうと思っているんだ」 「そうか、それはすばらしい。東京はダメだと向山さんにいわれているけど、東京の力を見せてやろうぜ」 「平和さんも、20本は持っていくだろう。光ちゃんは、今回12本持っていったんだから、20本は持っていけるでしょう」 阿部夫人が、とまどいながらもうなずく。 「阿部と私で100本、平和さん20本、光ちゃん20本か」 「そうだ、中島さんも入れよう。今回22本でトップだったから、氣をよくしているはず。20本は軽くいけるよ」 「うん、中島さんも入れよう」 「そうすると、東京で160本か。すごいね」 「そうだ、サークルでも記録を創ろう。サークルで160本、すごいね」 「愛知合宿に、『かけよってきました会』の岸さんが63本持っていったと誰かがいってたよ」 「そうか、50本じゃ記録にならないな」 「どうせなら…」※阿部氏は70本書くつもりだったとのこと。 「おまえ、100本ねらっているんだろう」(杉渕) 「ははっははっはは」※いまさら「70本といえなくなってしまった阿部氏 何を考えているのだ、この2人は。 50本でさえ普通じゃないというのに、100本とは… 仙台合宿まで、あと4か月である。 4か月間に100本書くのは不可能に近い。 しかも、印刷し製本するのにかなりの時間がかかる。 私は32本書いたとき(箱根合宿)でさえ、製本するのがいやになった。 まして、100本! それに、実践がなければ論文は書けない。 100本論文が書けるということは、それだけの実践があるということが前提になる。 次に、持続力が必要である。 それも、並大抵の持続力ではない。 驚異的なねばりがなくては書けない。 途中でいやになるのが普通だろう。 第3に、計画性が必要である。 まとめて、100本は書けない。 いいところ、30本くらいだろう。 1か月、20~25本ぐらい書かなければ100本いかない。 きちんと計画しなければならない。 第4に、行動力が必要である。 せっかく計画を立てても実行しなければなんにもならない。 論文100本書くことは、そうとうな荒行である。 阿部、杉渕は、この荒行に挑戦する。 限界への挑戦である。 論文だけなら、100本書ける。 しかし、私たちには他にもやることがたくさんある。 授業の準備をしたり、日記を見たり、学級通信を書いたり、デートをしたり(?)忙しいのである。 このように忙しい中、論文100本に挑戦するのである。 100本書けるかどうかは問題ではない。 10本書こうと努力するかどうかが問題なのである。 こんなことを聴いたら、松本氏はびっくりするだろう。 自分は50本で最高だと思ったら、100本書いているやつが2人いたなんて。 「もう1つ、記録があるぞ」 阿部氏がいった。 「なに?」 「箱根合宿では、杉渕が1位だっただろう。京都合宿では、中島さんが1位だっただろう」 「そうか、本合宿では、東京が2連覇しているんだ」 「そう。仙台合宿でも東京が1位をとろうぜ」 どうせやるなら、苦しいことは楽しくやろう。 まとめると、次のようになる。
仙台のあつい夏 ネーミングについて 東京の法則化サークル連合(といっても3つのサークルだが…)の名前を考えた。 東京連合、新撰組、熱血○○… いろいろ出されたが、いいものがなかった。 「そうだ、『仙台のあつい夏』というのはどう?」 「それはいい」 「いいねー」 「仙台の暑い夏」ではない。「仙台の厚い夏」であり、「仙台の熱い夏」である。 レジュメが厚い、ハートが熱い、この2つをかけたのである。 「よーし、石岡先生のまねして、ほら、『哲学の道』みたいな通信を書こう」 「それがいい」 こうして、『仙台のあつい夏』通信を書くことになった。 何号くらいいくであろうか。 ※ちなみに、この稿のほとんどは、『仙台のあつい夏』通信である。 ひさしぶりに燃えてきた。 私は、両方の拳に力をこめガッツポーズ。 男は燃えなくっちゃ! 100本への道 「やるぞー」といくら叫んでも始まらない。 行動しなければ。 行動の第一歩は、計画を立てることである。 論文にできそうなものはないか、今までの実践を振り返ってみた。 また、4~7月の間にどんな実践をし、論文にするかを考えた。
これくらいはある。 全部書けば、70本をこえてしまう。 探せば、書くネタはけっこうある。 この他に、「時間活用術」なども書ける。 4月からは ・文学教材 3~4 20~30本 ・説明文 1~2 5~10本 ・詩 2~3 8~10本 ・言葉遊びシリーズ 10本 ・社会、算数、理科、体育 10本 ・補教の授業はこれだ 5本 これで、60本近く書ける。 計130本は書けるものがある。 これら全部を書くのはきついが、とにかく、できるところまでやってみよう。 幸い、いっしょにバカをやってくれる仲間がいる。 8月1日までがんばりたい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
怒りをこめて書きまくれ 阿部 編 それは1年前の3月から始まった。私は東京青年塾に論文を持っていった。まだ教員になる前であり、私が書いた初めての論文でもあった。 「学芸会 演技指導の基礎基本」 私が論文を読み終えると、石黒 修氏はいった。 「実践がない」 4月、教員になり、やっと実践ができると思ったら障害児学級の担任であった。それまで普通学級でやりたいと思っていた実践ができないのである。 11月、授業がやりたいという一心で杉渕学級にいって立ち合い授業をやった。石岡房子氏の「かがやき」実践への挑戦であった。石岡氏はいった。 「キャリア不足なのよね」 教員になって、それに、こと授業ということに限れば毎日の実践でキャリアを積むこともできない。 今年3月、京都合宿において向山洋一氏は杉渕氏を中央事務局にと推した。しかし杉渕氏は断り、代わりに私を推してくれた。向山氏はいった。 「杉渕くんに比べて、論文数、実践の面で出遅れている。これは事実だし、仕方のないことなんです」 中央事務局の話は、私の頭の上を通り過ぎていった。そのとき、私はニヤリと意味なく笑った。そうすることでかろうじて自分のプライドを保っていた。 普通学級に変わりたいという私の願いはかなえられず、あと2年更に出遅れたままでいなければならない。 杉渕氏はいう。 「法則化運動で学んでいる教師の1年は、並の教師の10年に相当する」 これより20年の差をつけられてしまうのを、何もできずに手をこまねいているしかないのか。 法則化運動に参加しているが故に味わわなければならぬ、このもだえともがきの中で、石黒氏、石岡氏、向山氏のことばは、私を更に追いつめ、更に鞭打つ。 実践がない… 実践がない… キャリア不足… キャリア不足… 出おくれ… 出おくれ… 実践がない… 実践がない… 実践がない… キャリア不足… キャリア不足… キャリア不足… 出おくれ… 出おくれ… 出おくれ… ウーン、 おのれ石黒、石岡、向山…………! 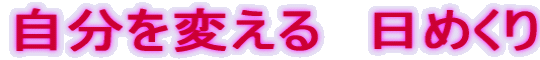 私は書く。論文を100本書く。怒りをこめて100本書きつづける。 100本の内訳を次のように考えた。
獲らぬ狸の皮算用ではある。しかし、現在確実に書けるものとして119本あるということは、目標達成の上でも大きい。 それに、今年は学芸会の年である。わが障害児学級も、学芸会に4月から取り組む。それもあわせて論文にしていけば、もっと増やすことができる。 問題は、それを書ききれるかどうかだ。時間的な問題ともいえるが、むしろ気力の問題である。気合の問題である。 私は書く 書いて書いて書きまくる。 怒りをこめて書きまくってやる。 それを一言でいうことにする。 すなわち 「怒[do]」 私の中にうっ積している不平不満の全てを、「怒」の精神で論文を書くことにぶつけることにする。 追試のできない今の境遇に対して…怒。 にもかかわらず黒帯資格の一つとして追試100時間とした向山上達論に対して…怒。 新採研の研究授業の授業者に立候補したのに、立候補したのは私だけであったのに、授業者似させてくれなかった指導主事に対して…怒。 校内研究に対してとりくみ方のあまい我が校の教員たちに対して…怒。 いまだに原稿依頼をよこしてこない明治図書編集部に対して…怒。 1か月2万円しかおこずかいをくれないうちの妻に対して…怒。 すぐインクもれと紙づまりをおこして手をわずらわせる我が校の印刷機に対して…怒。 私は自らの心の中に「怒」の文字を深く刻みこみ、心の中で叫びつづける。 怒りをこめて 書きまくれ! (注意) この通信を読まれた方は、たたりのおそれがありますので、般若心経を写経してください。 ウソ おそるべし 仙台の厚い夏 4月2日 阿部 野口芳宏氏の「ごんぎつね」の授業をビデオで観るため、臨時集会を開催した。 参加者(五十音順) 阿部 肇 阿部光江 杉渕鉄良 平和 修 宗像あいみ その場で、前々から電話で話し合っていた東京都連合サークル「仙台の厚い夏」を発足させることにした。 「仙台の厚い夏」は京都合宿の帰り、新幹線の中で杉渕氏との会話から考え出されたサークルである。 発足の主旨は、 一つのサークルで200本以上の論文を仙台合宿に持っていく ことであり、その目的は、 山と積まれた論文で壁を作り、他の合宿参加者にショックを与える。 ことである。 東京都連合サークル「仙台の厚い夏」のメンバーと論文本数ノルマを、私の独断で次のとおりとした。 阿部 肇 50本 杉渕鉄良 50本 平和 修 35本 中島祥広 35本 阿部光江 30本 ちなみに、京都合宿での論文本数一位は中島氏の22本。箱根合宿での論文本数一位は杉渕氏の32本。 サークルのメンバーの中に、過去一意経験者を二人も持っているが、今回のノルマは過去の記録よりもはるかに多い。どれもが論文本数一位を十分に狙える本数なのである。 サークルの活動は、 各自論文に対する取り組みを「仙台の厚い夏」通信に書く。それを美園座ぶどう塾に持ち寄り、発表することで互いに刺激しあい、ノルマ達成の発憤材料にする。 というものである。 まず「仙台の厚い夏」通信用のファックス原稿用紙が必要である。 そこでタイトルを印刷したファックス原稿用紙を400枚用意した。 杉渕氏に100枚、平和氏に00枚、それぞれ渡した。 「とりあえず10枚くらいもらっとこうと思っていたらいきなり100まいかよ」 と杉渕氏。なぁに、「仙台の厚い夏」が発足の目的を果たすために本格的な活動をはじめたら、400枚のファックス原稿用紙など、あっという間になくなってしまうさ。 京都合宿通信「哲学の道」は、創刊号で既に廃刊日を決めていた。 この東京都連合サークル「仙台の厚い夏」も、発足日に解散日を決めた。 東京都連合サークル「仙台の厚い夏」 昭和62年4月2日 発足 昭和62年8月2日(仙台合宿初日)解散 杉渕氏、平和氏、くれぐれもファックス原稿用紙を無駄にすることのないように。 夕食をとりながら、美園座ぶどう塾そして仙台の厚い夏の今後の運営について話し合った。 電話では、私の勝手に決めたノルマに「ええ!」と驚いていた平和氏も、私と杉渕氏の100本宣言に同調し100本を狙う意志表示をした。 これはスゴイ。はじめに私が立てたノルマなど、何となくちっぽけなものに思えてきた。とんだもないぞこのサークルは。久々にふるえた。武者ぶるいである。 私は100号を決死の覚悟で宣言した。しかし、それは1学期をこれ一つに絞ることを決心してものもだった。それでもなお、ひょっとしたら無理かもしれないという気がもたげてくる。杉渕氏はこの上に学級通信をB4で1000号をめざしている。昨年は、B5で1700号だから昨年よりB4で150号多く出すことになる。何てヤツだ。今、スタートが切られた。 阿部氏のやる氣 狂氣 4月3日 杉渕編 「仙台の厚い夏」の発足会が、4月2日、阿部氏の家でおこなわれた。 参加者は、6人。平和、阿部夫妻、杉渕、宗像、、そして、料理をつくってくれた光江さんの友人。 発足会は、6時開始の予定であったが、私は10分ほど遅刻してしまった。もうみんな集まっているかなと思いきや…まだ、だれもきていなかった。 「『仙台の厚い夏』の通信書いてきたぞ」 「えっ、早いなぁ」 「阿部は書いてないの?」 私は、阿部氏のことだから、10枚くらいは書いていると思って聴いたのである。 「いや、これ刷っててさ、表題(?)のデザインを決めるのに時間がかかっちゃってまだ書いてないんだ」 「そうか、もう10枚ぐらいは書いていると思ったよ」 「これ、どうだ」 と見せられたのが、東京都連合サークル 仙台の厚い夏という表題が印刷されたファックスの原稿用紙であった。 「はい」 とぽんとわたされた。大量のファックス原稿用紙である。 「なにっ、これ?」 「『仙台の厚い夏』の通信の用紙だよ」 「用紙ったって、おまえ、こんなに?」 「400枚印刷したんだ。杉渕は100枚書いてよ」 と、阿部氏はこともなげにいった。 なーに考えてるんだこいつは。まったく。 「仙台の厚い夏」のメンバーは5人。その5人で300号の通信を発行しようというのである。私には100枚書けという。 わずか4か月の間に100枚書けというのである。 私は、一瞬、阿部氏は氣が狂ったのではないか と思った。常識では考えられない。強烈なパンチである。 まあ、私に100枚書けということは、自分は200枚ぐらい書くということだろう。何しろ、阿部氏は「仙台の厚い夏」の編集長なのだから。と、私は通信で強烈なカウンターパンチをみまうのであった。 5人で通信を300枚書く。この通信は製本する予定である。そうすると、600ページの超大作になる。 私の持っているホチキスでは、300ページが限界である。2冊にわけなければ製本できない。 そんなことを考えているうちに、光ちゃんが帰ってきた。そして、平和氏もやってきた。 私は、平和氏にも(私が書いてきた通信№1~6を)わたした。 平和氏と阿部氏は、通信を真剣に読み出した。 途中で笑ったり、うなずいたりしながら2人は通信を読んでいた。 なかなかおもしろいということであった。 平和氏、阿部氏共に燃えてきたという。 平和氏のやる氣 狂氣 「そうか、杉渕さんは100本ねらっているのか…」 平和氏は、自分でいっていることを確かめるようにやや上を向き、ゆっくりといった。 「平和算は、20本?」 「いや、35本」 「えっ、ふやしたの?」 「昨日の電話で、阿部さんに『平和さんは35本ね』といわれたから」 まったく阿部はしょうがないなぁ。勝手に決めて。 まあ、平和氏なら35本くらいは書けるだろうと思っていたら… 「おれも、やってみようかなぁ…でも…テーマを決めて書けばいくかもしれない…」 「えっ、平和さん、やってみようというのは…まさか?」 そう、そのまさかだったのである。私は耳が壊れたのではないかと思った。 なんと、平和氏は、100本書くと宣言したのである。 ジャーン、出ました 平和氏の爆弾発言。 今日は、心臓によくない日だ。 「仙台の厚い夏」5人のうち、3人が100本をねらうというのである。これは狂氣としかいいようがない。そばで、光ちゃんがあきれていた。なお、光ちゃんは、30本書くそうである。 「ダークホースになる」 平和氏がいった。 あの、京都合宿の平和氏とは別人のように思えた。 合宿当日、初対面の人に手伝ったもらって論文と綴じたという あの平和氏が…学級通信に手を加えず、そのまま論文にしたという あの平和氏が…(反復による強調である。 西郷松彦) 私は、浦島太郎のような氣分になった。 ★すべては4月で決まる 論文を100本書く、「仙台の厚い夏」の通信を一人100枚書くという計画はビックである。 夢や目標は大きいほうがいい。 問題は、目標に到達するために「どのようにステップをふんでいくか」ということである。 まず、計画を立てること、次に行動にうつすことが大切である。 計画についてはすでに述べたので、ここでは、行動について述べる。 すべては4月で決まる 私は断言する。スタートダッシュをしなければ、100本の論文を書くことなどとうてい不可能である。 じっくりやろうなんて思っていたらダメである。スタートではずみをつけなければ、100本いかない。ぐわーっとやって、ペースをつくることが大切である。超ハイペースをつくることが、100本を可能にする、唯一の道である。 いずれ、スランプがくることは間違いない。 ペースに乗る前にスランプがきたらどうなる? つぶれるに決まっている。 スランプがきても大丈夫なように、かため書きをする。 最低ラインとして次のことをあげる。 ・論文を20~25本書く。 ・サークル通信を25枚書く。 これができなければ、夢は夢で終わるだろう。 3人がこのラインを達成すると、夢は夢でなくなってくる。 4月前半は、なにかと忙しい。この忙しい時期をがんばると、あとが楽である。 気候もよくなり氣力も充実する5月、たくさんの論文が書けるだろう。 体調を崩しがちな6月も、なんとか乗り切れるだろう。 最低ラインを論文20~25本としたのは、わけがある。4月は計画を立てなければならないからである。100本の論文を書くためにはどうするか? ・何を書くか ・いつ書くか ・どう書くか を考えなければならない。 本当は、30~40本としたいところである。しかし、計画を立てることにけっこう時間がかかると考えるので、20~25本とした。 最低ラインの次に、法則(?)をあげる。論文を書くための杉渕の法則である。 ・1週間で5本書く(地道に)。 ・やれるときはどんどん書く(一氣に) なにがなんでも、週5本書くのである。これは、最低ラインをさらに具体化したものである。あとでまとめてやろうとすると続かない。毎日の地道な努力が大切なのである。 しかし、毎日書くというのはきついだろう。いろいろな用事が入り書けないときもあるからである(毎日1本書くというのが理想であるが、無理だろう)。 書けない週は、土、日を使うしかない。 「あーあ、夏(8月1日まで)が終わるまでは、これ1本(100本の論文を書くこと)だなぁ」 と、平和氏はいう。 まさにそのとおりである。他のことをやる暇はない。遊んだり、デートしたりする暇はないのである。だから、私はデートしない(影の声…相手がいないのにデートできるわけがない。モテないのを正当化しようとしている)。 話を元に戻す。 週5本といっても、書けないときが必ずくるだろう。かぜをひいたときなど、1本も書けないかもしれない。 そんなときのために、貯金をしておくといい。 備えあれば憂いなし というではないか。 調子がいいとき、時間があるときは、どんどん書いて書きだめをするといい。 これは、『あらうま』(学級通信)を1700号書いたテクニックの一つである(原がダメなのは、かため打ちができないからである。落合がすごいのは、かため打ちができるからである)。 スランプのときは、貯金をおろせばいいのである。 以上のことをまとめると、 常に先手をとる ということである。 常に、先手先手でいくと余裕が生まれる。 精神的に楽になると仕事がはかどる。 流行作家なみ 「さあ、明日(4月3日)から論文を書こう」 「仙台の厚い夏」発足会で私はいった。 「おれ、もう5本書いたよ」 と阿部氏が衝撃的な発言をした。 「もうリードされている」 平和氏がいった。 先行逃げ切り型の阿部氏は、すでにスタートしていたのである(※持続力に難がある)。 しばらく沈黙が続いた。 3人は、いかにしたら100本書けるかといういことを考えていたのである。 阿部氏は、得意の学芸会、劇の指導を書くという。 平和氏は、教師修行を書くという。しかも、ありきたりのものではなく、どくとくのものを書くという。 どくとくと聴いたとき、私は吹き出してしまった。 平和氏は、もう本を出すときのことを考えているのである。氣がはやいというか、見通しをもっているというか、とにかくおかしくなった。 「これから、流行作家なみの生活になるだろう」(笑) 私はいった。 書かなければならないものがたくさんある。
1 論文100本 4か月で100本書かなければならない。月平均25本書くことになる。最低週5本書く。 2「仙台の厚い夏」通信 ノルマ100枚。現在11枚目を書いている。あと89枚。 3 学級通信 今年度も『あらうま』、ただしB4版で発行する。 目標、なんと1000号。1学期中に350~400書きたい。しかし、論文100本があるので書けるかどうか不安である。最低でも300枚書かないと1000号出せない。 4 サークル通信 有田氏の授業もまだテープおこしができない状態である。美園座ぶどう塾通信にあっという間に抜かされるだろう。 夏が終わるまでは、そう出せない。 5 雑誌原稿 明治図書から1本。〆切は5月20日、7ページである。他のところから1本、20ページ。4月13日まで。「仙台の厚い夏」通信を書いていていいのだろうか? 6 その他 全国の仲間への手紙など。 うーん、まさしく流行作家なみの超ハードスケジュール。夏まで生きていられるだろうか。 流行作家はつらい。 しかし、作家になった氣分でやるしかない。 私の平均的な1日の仕事は、次のようになるだろう。このスケジュールが7月まで続くのである。
1日(400字詰め原稿用紙に換算すると)20枚以上書かなければならない。 考えるだけで、おそろしくなってしまう。 何もない日はこれでいい。何とかできるかもしれない。 問題は、サークルなど用事がある日である。二次会も顔を出すとなると、ノルマの3分の1ぐらいいしかできない。 この日をどうするか? ・二次会に出ないで、帰って仕事をする。 ・学校にいる時間にできるだけやる。 ・電車の中で書く。 困った… 4月の予定を見てみよう。 次のようになっている。
これ以外に、練馬作文の会、ほっぷ4月例会が入ってくる。 とうてい全部は出られない。何かをカットしなければ… 土曜、日曜は、すべて論文書きで終わるだろう。 あーあ。 たとえ100本書けたとしても、バンザーイというわけにはいかない。2号にも書いたのだが、この後には、製本地獄が待っている。 論文100本ということは、一部につき150~200枚の紙を使うことになる。 これを200人分つくらなければならない。 一人でやったら、何日かかるだろう。 箱根合宿に持っていく論文(75枚)を製本したときでさえ、15~16時間かかった。 その2.7倍の時間がかかることになる。ということは、約43時間。 あの単純労働を43時間もしなければならないと思うと、頭がくらくらしてくる。 アルバイトを頼むか? こうなったら、わけてやるしかない。 つまり、1か月に2回ぐらいできた分を製本してしまうのである。 こうすれば、43時間続けてやらなくてすむ。 これしかない。わけてやろう。 ※1日5時間やったとしても9日間かかる。 10~15本書けたら製本してしまおう。 ぜんぶできたら、特大のホチキスでとじる。 ダンボール7~8箱になるだろう。 あまり先のことを考えると、やる氣がなくなってしまうから、考えないようにしよう。 ただ、高く積み上げられた論文の山を夢見て! しかも、一人ではない。サークル「『仙台の厚い夏』で300~400本の論文である) 「仙台の厚い夏」は、法則化運動の歴史に残るだろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||